お役立ち情報
- トップ>
- お役立ち情報
お役立ち情報
![]() 人気情報ランキング
人気情報ランキング
- 1【中国G18】 AIが好んで食べる情報、食べない情報 ( AI検索最適化 )
- 2【中国G15】 物来喜社のホームページの「制作力」を徹底解剖する
- 3【中国G20】 中国に学ぶ、日系企業が生き残る「官民連携」の本質
- 4【中国G19】「おすすめは?」の一言で、中国市場から消える日
- 5【中国G10】 中国の検索は「AI時代」に突入済(AI検索環境の変化)
- 6【中国G26】 最後のローカライズである日系企業「情報の現地化」
- 7【中国G14】 AI検索が変える中国ビジネス環境と日系企業の適応戦略
- 8【中国G28】 ホームページが映す、日系企業の「中国事業新時代」
- 9【中国D82】 DM1番目の理由は顧客の期待値やニーズを把握するため
- 10【中国D48】 第1位は中国でWeb集客したい(コンテンツSEOが主流)
【中国G29】 中国競争激化時代の差別化とホームページ刷新の決断2025.10.11
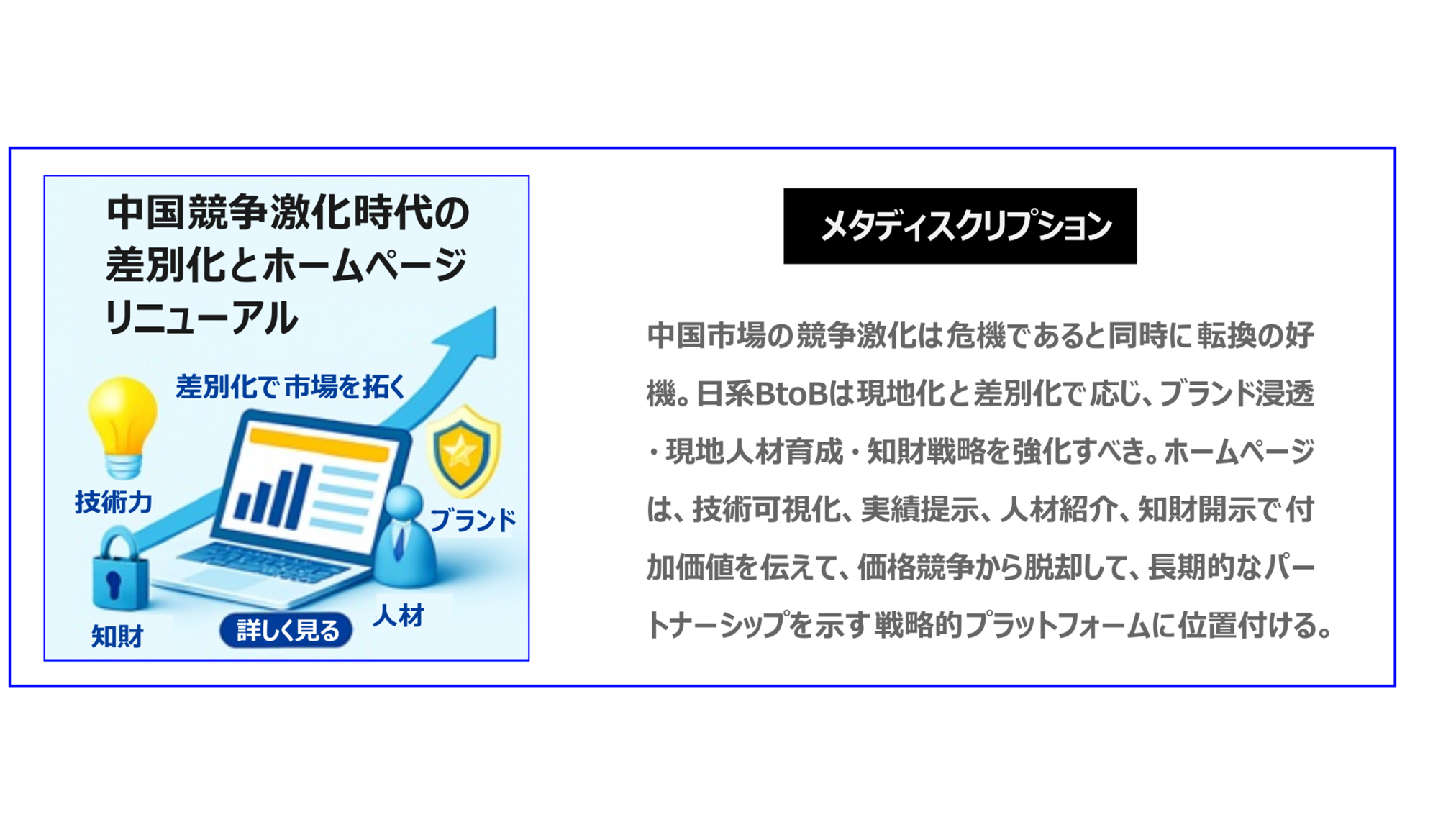
1. Web戦略の転換がもたらす新たな可能性
①変わりゆく中国市場の風景
最近、日系企業の経営者や、業界関係者との会話で、
頻繁に話題に上るのは「以前とは勝手が違ってきた」
という実感ではないでしょうか。
↓
この実感を裏付けるように、 日本貿易振興機構
(JETRO)が2024年に発表した「アジア・オセ
アニア日系企業実態調査」 では、 厳しい数字が
示されている。
②2024年に、営業利益を「黒字」となった
日系企業は 58.4%で、前年比 1.9ポイント低下。
特に製造業の中小企業では、
赤字比率が3割に迫る水準となっている。
↓
しかし、この数字を単純に悲観的に捉える必要はない。
むしろ、市場環境の変化を前にビジネスモデル
を「見直す絶好の機会」と 捉えるべきでである。
③今回は中国市場の現状と、BtoB企業としてどの
ようにWeb戦略を転換すべきか についてお話する。
2. 数字が語る中国市場の厳しい現実
①広がる地域格差とその背景
JETROの調査結果を詳細に分析すると、中国
国内で明らかな「地域格差」が 浮かび上がる。
↓
山東省、江蘇省、福建省では、
黒字企業の比率が上昇している。
一方、浙江省、重慶市では、
黒字比率が20ポイント以上も低下。
天津市では赤字比率が44.4%に達する。
②この地域格差は、単純に「良い地域」と
「悪い地域」と 区分けできるものではない。
それぞれの地域で産業構造や競争環境が異
なり、日系企業の「強み」が活かせる場面
とそうでない場面が明確になってきている。
(例❶)江蘇省では電子機器産業の集積が
進み、関連する日系部品メーカーにとって
は、追い風となっている。
Panasonicや 村田製作所などの日系企業が、
蘇州や無錫に生産拠点を集中させ、現地の
電子機器産業クラスターと連携している。
一方、重慶市では、自動車産業の変革により、
従来型の部品メーカーが苦戦を強いられている。
電気自動車 (EV) への急速な移行が、従来の自動
車部品サプライヤーに 大きな転換を迫っている。
③業種別に見る明暗の分かれ目
製造業の中でも、業種によって、
経営状況に明確な差が出ている。
⑴ 以下の業種が黒字を見込んでいる。
・電気・電子機器部品では 76.3%
・電気・電子機器では 73.9%
⑵ 以下の業種は黒字を見込んでいる数字が低い。
・鉄・非鉄・金属では 43.5%
・紙・木製品・印刷では 35.7%
⑶ 非製造業では、金融・保険業が100%黒字とい
う驚異的な数字を叩き出している一方、事業関連
サービスでは 37.8%にとどまっている。
④この違いはどこから生まれるのか。
答えは「現地化」と「差別化」の度合いにある。
↓
成功している業種は、中国市場の特性を理解し、
「現地ニーズ」に合わせたサービスを 提供して
いる傾向が顕著である。
3. 日系企業の強みと弱み(自己認識のギャップ)
①競合環境の激変
調査によれば、過去5年間で「競合企業が増加」
したと答えた日系企業は6割に上り、4割超が
「シェアの縮小」を経験している。
在中国日系企業の8割が以下と認識している。
「地場企業(中国企業)を最大の競合である」
↓
これは非常に重要なデータである。
日系企業は、もはや他の日系企業と競争している
のではなく「成長著しい中国企業」と直接に対決
せざるを得ない状況にあることを示している。
(例❷)ある自動車部品メーカーの担当者はこう語る。
「5年前までは、 同じ日系企業同士の品質競争が
中心でした。 しかし今では、中国企業の技術力が
急速に向上し、価格面では太刀打ちできない領域
が増えてきました。 BYDのような中国企業の技術
革新スピードには、正直驚かされます」
②強みと弱みの再定義
日系企業が自覚する強みは、以下。
・性能・品質の高さ
・アフターサービスの充実
弱みは「価格面」である。
↓
しかし、この強みだけに依存していては、
今後、ますます苦しくなると予想される。
理由は中国企業の品質も急速に向上しており、
「性能面での差」は、 年々狭まっているため。
③興味深いのは、 黒字かつ事業拡大を予定し
ている企業 (黒字・拡大企業) と、全体の回答
結果を比較したデータである。
黒字・拡大企業は、以下の3項目において、
全体を10ポイント以上上回る強みを感じている。
・性能・品質の高さ
・ブランドの浸透度
・人材
4. 成功企業に学ぶ差別化戦略
【差別化戦略❶】ブランド力という武器
黒字・拡大企業が 重視している要
素の一つが、 「ブランドの浸透度」。
↓
BtoB企業においても、ブランド力は重要である。
特に中国市場では「信頼できるパートナー」とい
う評価が、取引の決め手になることが少なくない。
(例❸)精密機器メーカーであるTHKの中国戦略
同社はブランド力強化のために、
以下のような取り組みを行っている。
⑴「技術ブログ」の継続掲載による認知向上
⑵ 業界紙への技術記事提供による専門性のアピール
⑶ 現地大学との共同研究による人材育成への貢献
↓
これらの活動は直接的な販促には繋がらないかもし
れないが、長期的なブランド構築には不可欠な投資。
【差別化戦略❷】人材戦略の重要性
もう一つのキーファクターが「人材」。
↓
成功している日系企業の多くは、現地人材
の登用と育成に、積極的に取り組んでいる。
(例❹)化学メーカーのダウ・ジャパン
同社では、管理職の7割を現地人材が占めて
おり、 意思決定のスピードと、現地市場への
適応力を高めている。
同社中国現地法人の総経理は次のように語る。
「日本人スタッフだけでは、 中国市場の細かな
変化に対応できません。 現地の優秀人材を登用
し、若いうちから責任ある立場を任せることで、
ビジネスの機会を逃さない体制を整えています」
【差別化戦略❸】知的財産の戦略的活用
黒字・拡大企業は「知的財産」へ
の意識が高いことも 特徴的である。
↓
単に特許を取得するだけでなく、
以下の戦略的思考を持っている。
「特許をどうビジネスに活かすか」
(例❺)村田製作所の中国戦略
同社は核心技術に関しては特許で保護しつつ、
周辺技術については意図的にオープンにして、
業界標準の獲得を目指す戦略を採用している。
↓
この「バランスの取り方」 が、同社
の中国市場での成功に 繋がっている。
5. ホームページリニューアルのポイント
①では「これらの知見」をどうやって、
ホームページ戦略に 活かせばよいのか。
単なる会社案内のホームページでは、
今や、誰も興味を示さなくなった。
↓
以下として、位置付ける必要がある。
「差別化要素を伝える重要なツール」
②具体的には、以下の4点が重要。
❶技術力の可視化:
専門技術をわかりやすく解説したコンテンツ
❷実績の具体化:
成功事例を詳細に紹介したケーススタディ
❸人材の紹介:
現地スタッフの声や技術者の紹介
❹知的財産のアピール:
特許技術や独自ノウハウの開示
③コンテンツ戦略の見直し
BtoB企業のホームページ訪問者は以下を求めている。
「専門的で信頼性の高い情報」
↓
コンテンツ戦略も、それに
合わせて見直す必要がある。
④効果的なコンテンツ戦略の
アプローチとして、以下が挙げられる。
❶業界課題へのソリューション提供:
顧客が直面している課題と、それに対する
自社の解決策を「技術ブログ」にして示す
❷技術資料の提供:
詳細な技術仕様書や ホワイトペーパー
を「ダウンロード」 できるようにする
6. 未来を見据えた戦略的転換
【戦略的転換❶】価格競争からの脱却
価格面での競争は日系企業の得意分野ではない。
↓
品質や信頼性、アフターサービスとい
った「付加価値」で 差別化を図るべき。
(例❻)工作機械メーカーDMG森精機の中国戦略
同社は、価格が中国企業の製品より3割高くても、
安定性と、精度の高さ、充実した技術サポートを
訴求することで一定の市場シェアを維持している。
↓
「安さだけでは買わない顧客」を的確にターゲッ
トにすることが、 重要であることを 示している。
【戦略的転換❷】デジタルシフトへの対応
パンデミック以降、商談や技術打ち
合わせのオンライン化が進んでいる。
↓
ホームページは、対面での接触機会が減少
する中で「自社の価値を伝える」営業効果
の高いチャネルとして重要視されつつある。
【戦略的転換❸】持続可能なパートナーシップの構築
中国市場で、持続可能なビジネスを展開するた
めには、短期的な販売利益だけでなく、長期的
な「パートナーシップの構築」が不可欠。
↓
ホームページを通じて、以下を伝える必要がある。
「顧客のビジネスを支えるパートナーであること」
(例❼)制御機器メーカーの三菱電機の中国戦略
同社は、顧客企業との「共同開発事例」をホー
ムページで詳細に紹介することで、 技術パート
ナーとしての姿勢をアピールしている。
↓
以下が、価格以外の差別化要因となっている。
「ともに課題を解決するパートナーの位置付け」
7. まとめ(変化を機会に変える思考法)
①中国市場の環境変化は厳しい挑戦ではあ
りますが、同時に大きな機会でもあります。
従来のビジネスモデルを見直し、
以下と捉えることが、重要です。
「真の強みを再定義する好機」
②調査結果が示すように、黒字を維持し成長を
続けている企業は、ブランドや人材、知的財産
といった「無形の資産」を活用し、価格競争と
は異なる次元で差別化を図っています。
③ホームページのリニューアルは、
「戦略的転換を具体化する」第一歩。
自社の強みを再定義し、 それを
「効果的に伝える」プラットフォーム
として、 ホームページを位置付けます。
↓
中国市場で持続可能な成長を実現するためには、
今こそ、 以下に取り組むべき時と気づくこと。
「ホームページ刷新を通じたブランド価値の再構築」
(参考:JETRO「2024年度アジア・オセアニア日系企業実態調査」)
(参考)ローカル企業の「強み」と「弱み」、日系企業が取るべき戦略
「この記事についてのご意見をお聞かせください」
ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。
※コンテンツは AI⽣成により基本⽂章を作成しています。
※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。
※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を
使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。
※ 弊社の「お役⽴ち情報」はスマホ画⾯で読む⽅が増えており、
スマホ画⾯で読みやすくすることを標準仕様としています。
ブラウザの設定画⾯にある「フォントサイズを調整すること」
で、格段に読みやすくなります。ぜひ、試してみてください。
本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。
無断転載・複製は、固くお断りいたします。
以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり
