お役立ち情報
- トップ>
- お役立ち情報
お役立ち情報
![]() 人気情報ランキング
人気情報ランキング
- 1【中国H01】 日系企業が競合に勝てない理由は 劣っているものがあるから
- 2【中国H18】 日系企業の弱点である「情報発信力」がホームページを変える
- 3【中国G97】 2025年中国検索市場、激動の真実と2026年「即実行」計画書
- 4【中国H23】 中国市場の新たな波に乗る(ローカル企業Web戦略から学ぶ)
- 5【中国H08】 AIが選ぶ時代の「勝ち組」サイト。検索され続ける必須7ヶ条
- 6【中国H09】 日系企業が持つ、中国市場に「響かない」「伝わらない」悩み
- 7【中国H26】 中国ホームページ大賞(企業ホームページの共感力革命)
- 8【中国H16】 2026年「伝わるホームページ」を持たない企業は消えていく
- 9【中国G42】 良質なブログが書けると会社とあなたに訪れる良いこと
- 10【中国H07】 ホームページリニューアルを怠ると信用が崩壊する7個の理由
【中国G30】 中国事業の拡大を目指す日系企業「ホームページ戦略」2025.10.11
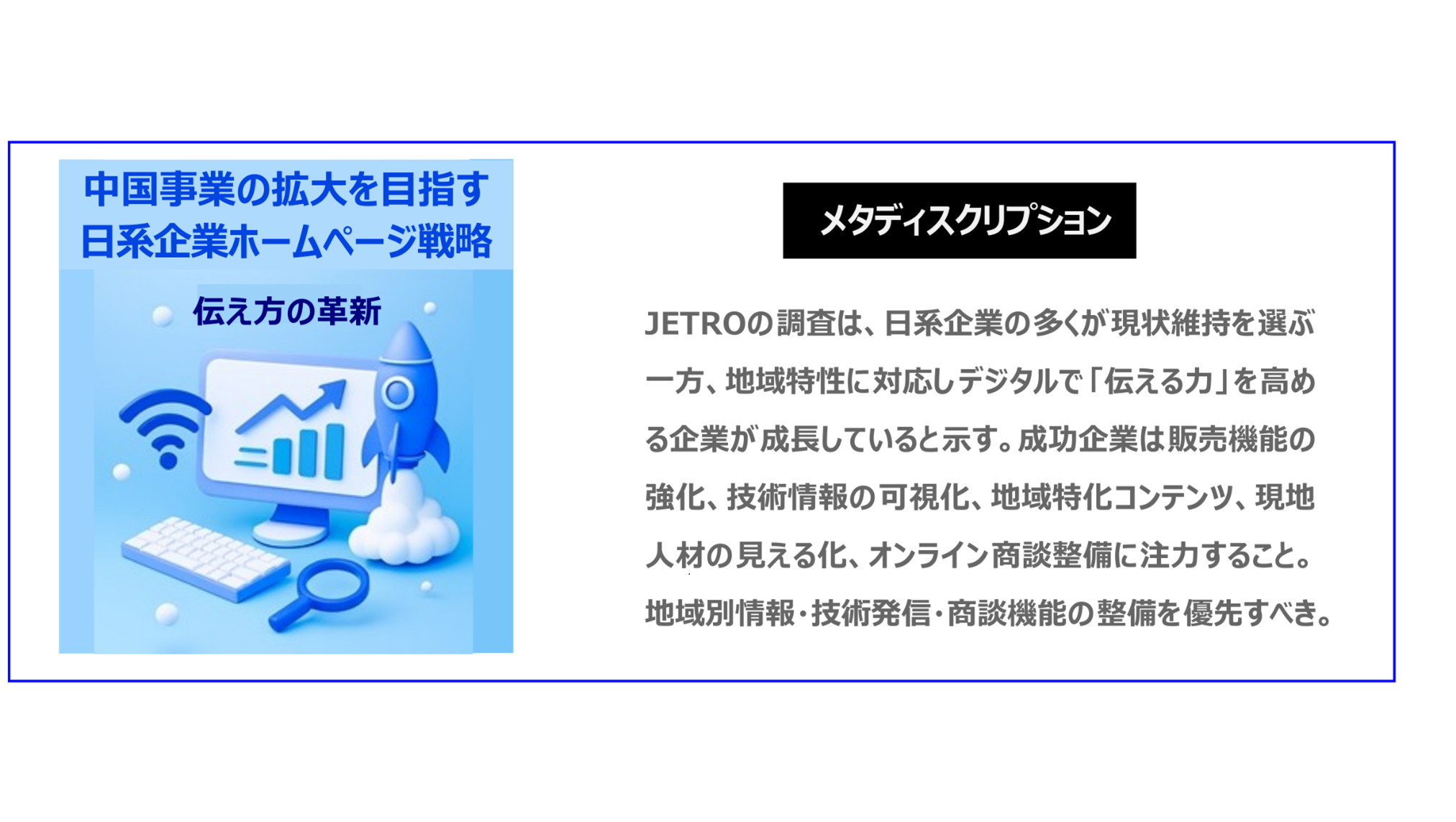
1. 数字が語る日系企業の「本音」と成長企業の共通点
①日本貿易振興機構(JETRO)が発表した
「2024年度 海外進出日系企業実態調査」
は、日系企業の現状を浮き彫りにしている。
この調査によれば、以下の企業が、
「事業を拡大する」と回答している。
・製造業では22.6%
・非製造業では20.5%
②逆に言えば、約8割の企業が「現状維持」か、
「縮小・撤退」を 考えているということになる。
この数字は日系企業が大きな転換点
に立たされていることを示している。
③しかし調査結果を深く分析すると、同じ厳
しい環境の中でも「確実に成長を続けている」
企業が存在するという事実が明らかになった。
彼らは何が違うのか。
↓
その答えはデジタル時代にお
ける「伝え方の革新」にある。
2. 拡大する企業と停滞する企業の決定的な差
①事業拡大への意欲はどこから生まれるのか。
業種によって、事業拡大意欲に大きな開きがある。
↓
製造業では、以下。
・食料品で 54.5%が「拡大」と回答している
・プラスチック製品では 12.0%にとどまっている
非製造業では、以下と回答している。
・小売業で 50.0%が拡大を目指す
②さらに興味深いのは、業種の特性だけでなく、
「どこで」ビジネスを展開しているかが 重要だ
ということ。
卸売・小売業に焦点を当てると、
山東省では 100%の企業が黒字で、
80.0%が事業拡大を志向している。
同じ業種でも、
・北京市では 66.7%が黒字、50.0%が拡大意向
・湖北省では 37.5%が黒字ながら、50.0%が拡大意向
③この違いは何を物語っているのか。
成功している企業は「地域特性」を深く理解
し、その土地に合ったビジネスモデルを構築
している。
↓
事業を「拡大」すると、答えた企業が注力している
機能についてのデータは、 非常に示唆に富んでいる。
・67.7%が「販売機能」の拡大に取り組む
・38.4%が「高付加価値品の生産」に取り組む
・27.4%が「新規事業開発」に取り組む
④これは単なるコスト削減や効率化ではなく、
「攻めの経営」に転じていることを意味する。
上海市では、88.5%の拡大企業が「販売機能の強化」
を掲げており、地域別で最も高い数値となっている。
3. 現状維持企業の「生き残り戦略」に学ぶ取り組み
①現状維持と聞くと、消極的
な印象を受けるかもしれない。
しかし調査結果を見ると「現状維持企業」こそ、
実に 多様な取り組みを行っていることがわかる。
②総合では現状維持のために、
以下のように取り組んでいる。
・日系企業以外への販路拡大など新規販路開拓に 44.3%
・これまでとは異なる分野・地域への販売拡大に 42.2%
・コスト削減に 39.4%
(例❶)ある産業用機械メーカーの担当者は、
現状維持の本質を次のように語る。
「現状維持というのは、 何も変わらないという
意味ではありません。 むしろ、激化する競争環
境の中で 現在のポジションを維持するためには、
絶え間ない改善と適応が必要なのです」
③業種別のデータは興味深い事実を明らかにしている。
⑴ 輸送機器部品では、73.2%が以下に取り組む。
「日系企業以外への販路拡大」
これは、日系自動車メーカーとの取引に依存
する従来のビジネスモデルから脱却し、中国
企業や欧米企業への「販路を広げる企業」が
増えていることを示している。
⑵ 情報通信業では、60.0%が以下に注力。
「これまでとは異なる分野・地域への販売拡大」
デジタル技術を活用し、これまでとは異
なる産業や、地域への進出を図ることで
「新たな成長機会」を模索している。
(例❷)化学メーカーのデジタルマーケティング投資
ある化学メーカーは、現状維持のために
「デジタルマーケティング」に 本格的に
投資することを決定した。
具体的な取り組みとして、以下を導入した。
・ホームページを全面リニューアル
・技術ブログ記事の継続掲載
・オンラインの技術相談機能
↓
これらの施策により、問い合わせ数が
大幅に増加し、新規取引のきっかけを
多数創出することに成功した。
4. アフターコロナの教訓
(人材育成とデジタル化の本格展開)
【教訓❶】アフターコロナに実施した取り組みとして
55.2%の企業が「現地人材の育成」を挙げている。
これは、 パンデミックによる渡航制限などで、
日本からの駐在員派遣が、困難になったことへ
の対応でもあるが、それ以上に「現地市場」を
深く理解した人材の重要性が再認識された結果。
②製造業に限ると、以下。
・現地人材の育成は:51.5%
・設備の増強:30.3%
・生産品目の多品種化:27.1%
特に北京市では 64.4%、天津市では 63.2%
と、北部の地域で「現地人材育成への関心」
が高いことが分かる。
【教訓❷】パンデミックをきっかけに、
多くの企業で、 デジタル化が加速した。
対面に依存していた業務のデジ
タル化が進み、以下が普及した。
・オンライン商談
・リモート技術サポート
・デジタルマーケティング など
5. 地域別・業種別成功パターンの詳細分析
【分析❶】長江デルタ地域の強さ
(輸送用機器・部品の場合)
輸送用機器・部品業種に焦点を当てると、
上海市、江蘇省、浙江省の長江デルタ地域では、
過半数が黒字であり、かつ拡大意欲が業種平均
(17.2%)を上回っている。
広東省、湖北省では、赤字企業が多い。
湖北省では縮小と移転・撤退の合計が半数に迫る。
②この違いはどこから生まれるのか。
長江デルタ地域には、サプライチェーンが集中
しており「技術の進化に対応した」迅速な開発
・生産が可能であるという強みがありる。
また「地元政府の支援体制」も整って
いることが競争優位性に繋がっている。
【分析❷】電気・電子機器業種の明暗
①電気・電子機器(部品を含む)業種では、
全体の 75.4%が黒字と、比較的好調。
特に江蘇省では80.0%が黒字で、拡大意欲も、業種
平均(22.2%)を 大幅に上回る37.5%となっている。
②この背景には江蘇省における電子機器
産業の「集積」と、地元大学との「連携」
にる人材育成の充実がある。
蘇州、無錫、常州を中心とした地域には、
国内外の 主要電子部品メーカーが 集中立地し、
「効率的な」サプライチェーンを形成している。
(例❸)電気機器メーカーの産学連携
ある電気機器メーカーは、現地の大学と
共同研究所を設立し、卒業生を優先採用
するシステムを構築している。
これにより、 質の高い人材を確保しながら、
最新の研究動向を ビジネスに活かす好循環
を生み出している。
↓
同社のホームページには「共同研究の成果」
や「技術論文」が詳細に掲載され、技術的
な信頼性をアピールしている。
6. ホームページリニューアルで実現すべき変革
【変革❶】ブランドストーリーの再構築
①黒字・拡大企業は以下に強みを感じている。
「ブランドの浸透度」
②BtoB企業においてもブランドストーリーは重要。
ホームページでは、 自社の技術力や、品質への
こだわりだけでなく、以下を伝える必要がある。
「どのような価値観で事業に取り組んでいるか」
(例❹)ある化学メーカーは、ホームページに
「技術者の想い」というコーナーを設け、開発
に携わる技術者のインタビューを掲載した。
製品のスペックだけでなく、開発背景や 社会へ
の貢献を伝えることで「共感」を生み、 単なる
価格競争とは異なる次元での差別化に成功した。
【変革❷】技術情報の「見える化」
BtoB企業のホームページ訪問者は、
「専門的な情報」を求めている。
↓
成功している企業は、技術ブログや、ホワイト
ペーパーを充実させ、訪問者が「自社の技術力」
を詳細に理解できるようにしている。
【変革❸】地域特化型コンテンツの提供
事業の成功は「地域」と深く結びついている。
↓
ホームページでは、 特定の地域向け
のコンテンツを提供することが有効。
(例❺)ある産業用材料メーカーは上海市
向け、広東省向けなど「地域別に特化した」
コンテンツを制作した。
各地域の産業特性や規制に対応した情報
を提供することで、 現地の顧客ニーズに
きめ細かく応えることが可能になった。
例えば、以下のように重点的に提供している。
・華南地区向けには電子機器メーカー向けの素材情報
・華東地区向けには自動車部品メーカー向けの技術情報
【変革❹】現地人材の「見える化」
現地人材の育成が重視される中、ホームページ上
で現地スタッフを紹介することは、企業の「現地
化への取り組み」をアピールする有効な手段。
【変革❺】デジタル商談環境の整備
アフターコロナの新しい常態と
して、オンライン商談は不可欠。
↓
ホームページには、以下の機能
を組み込むことが効果的である。
・無料相談機能
・オンライン商談の予約機能
・製品デモンストレーションの申し込み機能
7. まとめ(変化を成長の機会に変えるための決断)
①中国市場の環境変化は、確かに厳しい挑戦です。
しかし、調査結果が示すように、同じ環境
の中でも成長を続けている企業があります。
↓
彼らは、変化を恐れるのではなく「新たな機会」
として捉え、ビジネスモデルや、コミュニケー
ション方法を進化させてきました。
②ホームページのリニューアルは、 ビジ
ネスそのものの変革を反映するものです。
自社の強みを「再定義」しそれを「効果的に伝える」
プラットフォームとして、 ホームページを位置付け
ることで、 新たな成長軌道を見出すことができます。
③ビジネスの世界では、以下の言葉があります。
「変わらなければ、変わられてしまう」
④中国市場で 今後も 生き残るために、 今こそ、
「ホームページ」を通じたビジネス変革に挑戦
する時です。
デジタル時代の伝達手段として、 ホームページ
はビジネスそのものを「変革する触媒」となる
可能性を秘めています。
↓
具体的な行動として、 以下の課題を洗
い出すことから始めてみてはいかがか。
・自社のホームページを客観的に評価
・地域特化型コンテンツの不足
・技術情報の不十分な可視化
・オンライン商談機能の未整備 など
⑤中国市場における次の成長段階は、以下に
かかっていると言っても過言ではありません。
「効果的なデジタルコミュニケーション戦略」
(参考:JETRO「2024年度海外進出日系企業実態調査」)
(参考)今、百度ランキングを向上させる「滞留時間戦略の核心」
「この記事についてのご意見をお聞かせください」
ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。
※コンテンツは AI⽣成により基本⽂章を作成しています。
※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。
※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を
使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。
※ 弊社の「お役⽴ち情報」はスマホ画⾯で読む⽅が増えており、
スマホ画⾯で読みやすくすることを標準仕様としています。
ブラウザの設定画⾯にある「フォントサイズを調整すること」
で、格段に読みやすくなります。ぜひ、試してみてください。
本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。
無断転載・複製は、固くお断りいたします。
以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり
