お役立ち情報
- トップ>
- お役立ち情報
お役立ち情報
![]() 人気情報ランキング
人気情報ランキング
- 1【中国H01】 日系企業が競合に勝てない理由は 劣っているものがあるから
- 2【中国H18】 日系企業の弱点である「情報発信力」がホームページを変える
- 3【中国H27】 カギダンスから学ぶBtoB企業ホームページの「共感進化論」
- 4【中国H23】 中国市場の新たな波に乗る(ローカル企業Web戦略から学ぶ)
- 5【中国H30】 バランスシート不況を生き抜く「デジタル母工場」構築戦略
- 6【中国H08】 AIが選ぶ時代の「勝ち組」サイト。検索され続ける必須7ヶ条
- 7【中国H09】 日系企業が持つ、中国市場に「響かない」「伝わらない」悩み
- 8【中国H26】 中国ホームページ大賞(企業ホームページの共感力革命)
- 9【中国G42】 良質なブログが書けると会社とあなたに訪れる良いこと
- 10【中国H07】 ホームページリニューアルを怠ると信用が崩壊する7個の理由
【中国F95】「コンテンツ不足」の不可視ホームページが生む致命性2025.09.04
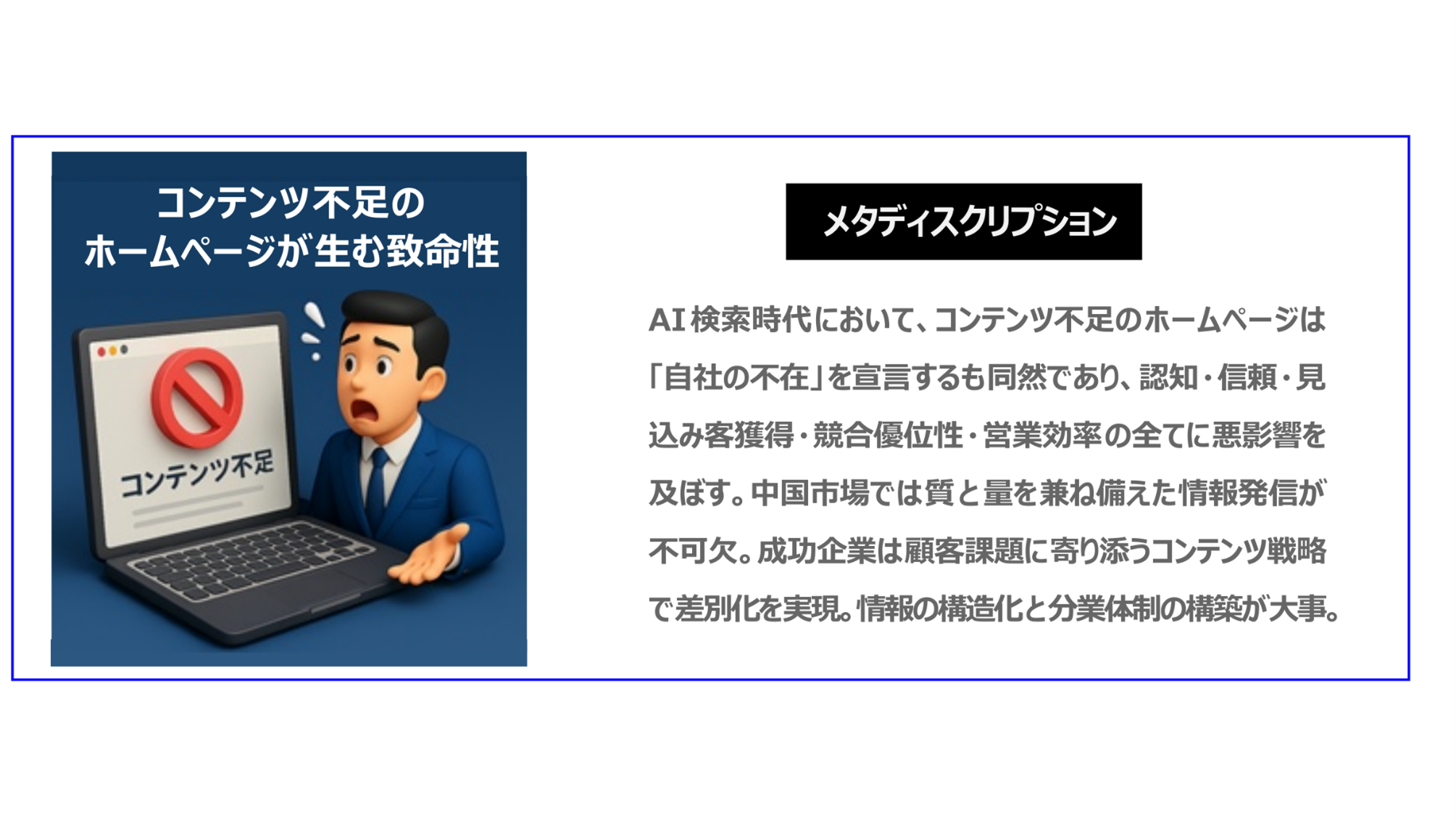
1. AI検索時代の「自社の不在宣言」
①いつも自社のホームページを育てること
にどれだけの時間と情熱を注いでいますか。
「名刺にURLを載せるため」だけ
の存在になっていないだろうか。
↓
中国市場で ビジネスを展開する日系企業にとっ
て、 それはもはや「ない方がマシ」 ですらある。
②理由は、AI検索エンジンが台頭する現在、
「コンテンツ量が乏しいホームページ」は、
自社の不在を 宣言しているに等しく、顧客
にマイナス効果を与えているため。
コンテンツとは、ホームページ内に掲載されている
文章・画像・動画や、それらが表現する情報のこと。
2. AI検索エンジンは「質」と「量」の両方を求める
(なぜコンテンツ不足が致命傷になるのか)
①昨今の検索エンジンは、より自然な会話型の検
索に対応するために、大規模言語モデル (LLM) を
活用した AI検索機能を次々と導入している。
これらの AI検索エンジンは、ユーザー
のクエリに対して直接答えを生成する。
↓
その答えの源は世界中のホームページを
含むWeb上に存在するコンテンツである。
クエリとは、ユーザーが検索エンジンに入力した語句や文章のこと。
②では、 もし貴社のホームページに、以下の
ような状態が 蔓延していたら、何が起きるか。
❶自社製品の技術仕様や適用事
例が「詳細に記載されていない」
❷企業の強みや、差別化要素が、
「抽象論に終始し」具体性に欠ける
❸企業の創業のストーリーや理
念、 価値観が「伝わってこない」
❹業界のトレンドや 課題についての深い
「洞察を示す」コンテンツが 存在しない
③答えは単純明快である。
AI検索エンジンが ユーザーの質問に答える際に、
貴社のホームページは「情報源」 として、一切
参照されなくなることが起きる。
↓
つまり、潜在顧客がどんなに詳細な質問を投
げかけようとも、貴社はその会話のテーブル
に着くことすらできなくなるということ。
3. コンテンツ不足がもたらす機会損失
(他社に先行される日系企業の残念な現実)
①コンテンツが少ないことの弊害は、AI
検索で 「無視される」ことだけではない。
②総合的に見て、以下の機会損失を生み出している。
【機会損失❶】認知機会の損失
検索エンジンでのあらゆるキーワ
ードで「発見される機会を逸する」。
↓
認知度が低い日系企業ほど、
情報発信量が生命線である。
【機会損失❷】信頼構築の失敗
詳細な技術情報や、ケーススタディ
は、 BtoB取引における「信頼の礎」。
↓
それがないことは「自社商材に自信
がない」と宣言しているようなもの。
【機会損失❸】見込み客獲得の不全
見込み客は「疑問を解決する」
過程で購買プロセスを進める。
↓
各段階で必要な情報がなければ、
次のステップに 進むことはない。
【機会損失❹】競合優位性の崩壊
競合他社が 詳細なコンテンツで差別化を
図っている中で 「自社が陳腐な内容しか」
提供できなければ、 購買担当者が比較検
討する段階で、真っ先に除外される。
【機会損失❺】人的リソースの浪費
「社内に書く人がいない」は最大の言い訳。
↓
しかし、その状態を放置することこそが、
営業部隊の戦力を削ぎ「説明コスト」を
膨大に増加させている真因である。
4. 日系企業のホームページがコンテンツ量が少ない現実
①日系企業のホームページは しばしば
「コンテンツ不足である」 と指摘され
るが、具体的にはどの程度なのか。
驚くべきことに、自社の製品や技術を紹介する
「主要ページが10ページ未満」であるケースが
少なくない。
例えば、 企業概要や、製品カテゴリー数ページ、
問い合わせ先だけで 構成されている 貧弱なサイ
トも散見される。
②これは、中国市場における一般的なBtoB
企業が 目指すべき「50ページ以上」という
ボリュームとは大きく乖離している。
このコンテンツ量の差が AI検索エンジン
での「可視性に直結すること」に繋がる。
③ユーザーが詳細な技術用語で検索して
も、貴社のページに 十分な情報がなけれ
ば、AIは答えを導き出せない。
つまり、ページ数が少ないことは、
それだけで機会損失を生んでいる。
↓
以下が、AI検索時代の最低条件である。
「まずはコンテンツの量を確保すること」
5. コンテンツの「量」と「質」で差別化を実現した事例
①では、具体的に何をすればよいのか。
コンテンツ戦略において、成功を収めて
いる企業の事例は、最良の教科書である。
(事例❶)キーエンス中国
中国市場において、キーエンスは単なる製品
カタログを超えた、極めて詳細な技術解説や
導入事例を豊富に提供している。
キーエンス中国 ホームページの ページ
数は優に3,000を超えると言われている。
例えば、ある特定のセンサー製品について、
その動作原理から、他社製品との性能比較、
具体的な応用シーンでの設定方法までを網
羅した技術資料を公開している。
↓
これはエンジニアという高度な知識を求
めるユーザーに対して、 検索エンジンを
通じて「圧倒的な価値を提供し」 強固な
信頼を築している好例と言える。
(事例❷)オムロン中国
オムロンは、中国の産業用オートメーショ
ン市場において、自社の技術領域に関する
「課題解決型」のコンテンツを大量に生成
している。
例えば、製造現場の省人化に関するホワイト
ペーパーや、特定の工程における自動化ソリ
ューションの導入例を詳細に掲載している。
↓
ユーザーが産業課題に関する検索を行った
際に「オムロンの知見」 に必ず触れられる
環境を構築している。
(参照:オムロン中国のホームページ)
②これらの企業に共通するのは、
「自社の製品を売りたい」ではなく、
「顧客の課題を解決したい」という視点で
コンテンツが、構成されている点である。
結果として、コンテンツの「量」は自然と
増え、それが AI検索エンジンからも、高く
評価される好循環を生み出している。
6. コンテンツ量を飛躍的に増大させる実践戦略
「社内に書く人がいない」という
壁は現代ではもはや存在しない。
↓
それを打破する具体的な方法論は、以下。
【方法論❶】既存情報の構造化
まず社内に散逸している情報をかき集めること。
↓
以下を整理し、Web掲載可能な形に、再構成するだ
けで「数十ページのコンテンツ」が瞬時に生まれる。
・製品マニュアル
・技術資料
・営業が作成したプレゼン資料
・Q&A集
【方法論❷】インタビューの力
現場のエンジニアや、 営業担当者、
経営者にインタビューをすること。
彼らは誰よりも自社の強み
と顧客の課題を知っている。
↓
「その生の声を記事化すること」は、最高の
質と量を兼ね備えたコンテンツ生成法 である。
【方法論❸】外部リソースの活用
ホームページ制作会社や、
AI生成ツールを活用すること。
↓
社内のナレッジを提供し、専門家がコンテ
ンツに仕上げる「分業体制を構築すること」
は、最も現実的で効率的な解決策である。
【方法論❹】コンテンツの細分化と多元的展開
1つの大きなホワイトペーパーを要約した
ブログ記事、さらにそれを動画や インフォ
グラフィックに展開する。
↓
このように1つのテーマを多角的に掘り
下げ「複数のコンテンツに仕上げること」
で、効率的に量を増やすことができる。
7. AI検索エンジン最適化の核心
(コンテンツの「E-E-A-T」を強化すること)
①「E-E-A-T」は、 AI検索時代に
おいてさらに重要性を増している。
E-E-A-Tとは、Experience:経験、Expertise:専門性、
Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性のこと。
②生成AIは、これらの要素を備えた高品
質で「信頼できる情報源」を強く求める。
③量を増やすことは土台である。
しかし、その土台の上に、自社の「経験」
と「専門性」に基づいた 深い洞察を示す
コンテンツを築き上げる必要がある。
↓
それは自社が誰よりもその分野について
熟知しているという「権威性」を醸成し、
結果として、 顧客からの絶大な 「信頼」
を獲得するに至る。
8. まとめ(コンテンツなきところに認知も信頼もなし)
①コンテンツなきところに、認知も信頼もなし。
まずは「量への挑戦」から全ては始まります。
↓
中国市場において、認知度が 決して高く
ない日系企業が生き残る道は、ただ一つ。
情報発信量で圧倒し、AI検索エンジンから
「答えられる企業」として認知されること。
②「書く人がいない」は過去の遺物。
現代は「書く意志」があるか
どうかのみが、問われます。
↓
書くことは「慣れ」 であるため、書かない
ままでは、 いつまでも状況は変わりません。
物来喜社では、ホームページ制作をご依頼い
ただいた企業様に書き方をお教えしています。
物来喜社のブログ記事(お役立ち情報)
の記事数はすでに 約600になりました。
③自社ホームページを、顧客との会話を生み続け
る「生きている」資産へと変える旅を始めること。
それが、AI検索時代という荒波を勝ち
抜く「唯一確実な羅針盤」となります。
(参考)「情報が少ない」ホームページでは、認知されない。信用されない。
「この記事についてのご意見をお聞かせください」
ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。
※コンテンツは AI⽣成により基本⽂章を作成しています。
※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。
※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を
使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。
※ 弊社の「お役⽴ち情報」はスマホ画⾯で読む⽅が増えており、
スマホ画⾯で読みやすくすることを標準仕様としています。
ブラウザの設定画⾯にある「フォントサイズを調整すること」
で、格段に読みやすくなります。ぜひ、試してみてください。
本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。
無断転載・複製は、固くお断りいたします。
以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり
